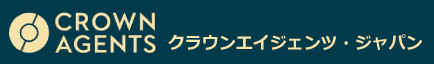当社のブログ第2回は、若手社員として活躍し、このたび出産というライフイベントを迎える萩原夏子さんにご登場いただきました。 CAJでは、すべての社員が安心してキャリアを築き、人生の変化にも柔軟に対応できる職場づくりを大切にしています。
今回は、萩原さんに入社の経緯や現在の業務、そして仕事と生活のバランスについて伺いました。(広報)
萩原さんがCAJに入社する前にされていたお仕事と、CAJへの転職を決めた理由などを教えてください。
(萩原)
 (社内での萩原さん)
(社内での萩原さん)
前職は、私立の国際教育に力を入れた中高一貫校の英語の教員として働いていました。
元々は、大学卒業後にJICA海外協力隊として、東アフリカのウガンダの村の小学校で教員としてボランティア活動をしていたため、国際協力分野の職種にいつか戻りたいと思っていました。これまでは草の根目線での国際協力を経験していたため、次は国家の事業としての大きな視点での国際協力に携わりたいと思い、CAJへの転職を決めました。
 (ウガンダの村の小学校で算数の授業をして、子供たちができた回答を見せに並んでいるスナップ)
(ウガンダの村の小学校で算数の授業をして、子供たちができた回答を見せに並んでいるスナップ)
 (赴任先の小学校とは別に、首都のスラム街で支援活動をはじめ、子供たちに体育の授業をしている萩原さん)
(赴任先の小学校とは別に、首都のスラム街で支援活動をはじめ、子供たちに体育の授業をしている萩原さん)
(広報)
現在担当されているプロジェクトや、印象に残っているお仕事について教えてください。
(萩原)
外務省の無償資金協力経済社会開発計画では、インドネシアのX線、ザンビアの獣医学機材と廃棄物収集車、ウズベキスタンの医療コンテナ案など、JICAのウクライナ緊急復旧計画では教育分野とエネルギー分野での案件を担当しています。特に印象に残っている仕事は、ウクライナ案件とウズベキスタン案件です。
(広報)
ではまず、ウクライナ案件について教えて下さい。
(萩原)
ウクライナ案件では、ウクライナへの緊急支援ということもあり、戦場地でのリアルなひっ迫した状況がウクライナ先方政府からの要望に繋がっています。これまでは、ニュースでしか知ることのできなかったウクライナでの厳しい現状を、案件を通じて直面し、私たちの仕事の進捗如何によって、ウクライナの人々がすぐに日本からの支援を受けることができるかどうかが関わっていることや、私たちがいくら頑張って進めても、戦地の状況によっては、各種手続きが遅れたり、連絡が取れなくなってしまったりと、すぐに支援を届けたいのに、できない、というもどかしさや悔しさを感じることがありました。私は実際にウクライナへ出張はしていませんが、同僚が出張をした際に、無事に支援物資が届き、特に教育分野ではウクライナの子どもたちがそれを実際に手に取り、授業をしている姿を見た時には、大きな達成感がありましたし、私たちの仕事への重みも感じました。
(広報)
それではウズベキスタン案件では如何ですか?
(萩原)
ウズベキスタンは私にとって初めて最初から担当させて頂く案件でした。案件開始時にはウズベキスタンへも出張に行き、現地視察や先方政府と話し合いを行いました。初めて自分で先方政府へ直接説明をしたり、要望を聞いたり、実際の現場を見に行ったりすることで、この案件に対する責任もより強く感じました。国同士の事業ではあるのですが、実際にはこうして人対人で様々なことを調整し、一緒に案件を完成させていくのだということや、ウズベキスタン政府とも、チームであることを感じることができました。その後も、たくさんの調整が必要で、中々一筋縄ではいかないことも多いのですが、その国ごとの事情や現状に合わせて、いかに柔軟に調整していくかがカギとなり、その都度解決策を考えていくことにも醍醐味を感じています。
 (ウズベキスタン出張の際に、以前別の案件で納品された医療コンテナの利用状況を視察している様子)
(ウズベキスタン出張の際に、以前別の案件で納品された医療コンテナの利用状況を視察している様子)
 (ウズベキスタン政府との政府間協議会で議事録に署名をしている様子)
(ウズベキスタン政府との政府間協議会で議事録に署名をしている様子)
(広報)
実際に担当してみて、やりがいを感じた瞬間や成長したと感じる出来事はありますか?
(萩原)
実際に調達した資機材支援物資が現地に届いて、現地の人々が喜んでいる姿を見たり、うまくいかない状況に対して考えた解決策がうまく働いたりした時などは、とてもやりがいを感じています。また、この1年で最初はすべてを先輩社員の方々から教えてもらわなければできなかったことが、今では何か起きた際に、まずは自分で考えた解決策を先輩社員の方に提案し、それに賛成していただいた時などは、少しずつ仕事を覚え、経験を踏んだおかげで解決策も少しずつ自分で考えることができるようになっている、という成長を感じます。また、先輩社員からもたくさんの励ましやお褒めの言葉をいただき、より頑張ろうという気持ちに繋がっていてとても感謝しています。
(広報)
それは何よりですね。職場の雰囲気や、チームでのやり取りについてどのように感じていますか?
(萩原)
新入社員として入ったばかりの頃から、どの先輩社員の方も、案件ごと1つ1つ丁寧に1から教えていただき、前職とは全く違う職種であるのに、皆さん温かく受け入れてくださり、本当に働きやすかったです。どの案件も1人で背負っているという気持ちはなく、必ず上司がついてくださり、大きな案件ではチームで対応しているので、困ったときもすぐに相談できる環境だと思います。様々な経験のある先輩社員の方々から色々なお話を聞けることも多くの学びに繋がっています。仕事だけでなく、休憩時間には世間話を交わし、心の余裕もでき、CAJの会社の一員になってきたと感じることはとても嬉しいです。また、ウクライナ案件、ウズベキスタン案件、ガーナ案件では、実施促進を担当する現地や近隣国の海外のエージェントの方とお仕事をしていて、彼ら彼女らからもたくさんのサポートをもらっているため、よりチーム一丸となって働いていることを沢山感じます。
(広報)
萩原さんから見てCAJの働きやすさや、柔軟な働き方について感じていることがあれば教えてください。
(萩原)
特に前職が教員であったこともあり、CAJの働きやすさは、入社した直後から感じています。フレックス制度や在宅勤務制度があることで、東京都外に住んでいても、自由に通勤時間を調整して出勤することができたり、在宅勤務日を調整したりすることできます。業務の内容上、他国と関わって仕事をしているため、急に忙しくなったり、急に少し余裕ができたりすることがあり、状況に応じて有給休暇も事前に柔軟に申請することができたりすることも大変ありがたいことだと思っています。有給休暇も1年目から沢山いただけたことや、状況に応じて長期で休暇をいただけたことも助かりました。また、妊娠が発覚してからは、私の場合は、つわりが重かったため、上長に相談し、在宅勤務日を多くしていただいたことも大変感謝しております。その後の妊婦検診のための傷病休暇も、案件の状況に応じながら、自由に取得させていただくことができたことにも、感謝の気持ちでいっぱいです。
(広報)
会社としてのバックアップも感じることが出来ましたか?
(萩原)
はい。会社全体で、仕事のことよりもいつも私の体のことを第一に気にかけてくださっていたことも多くの場面で感じており、本当に感謝しております。社員が働きやすいように、働き方の改善を都度行ってくださっていることや、社員の成長を促し、モチベーションを上げるためのグレード制度、マンツーマンでの社長や上長との面談の機会等も、それぞれの社員のことを見てくれている、という安心感にも繋がり、より頑張ろうと思えました。
産休に入る時期への相談もすぐに受けてくださり、引継ぎの段取りなども丁寧に指導頂き、本当に助かりました。引き受けてくださる先輩社員の方々には、業務が増えてしまい申し訳ないという気持ちもありますが、皆さん快く引き受けてくださったことには大変感謝しております。
(広報)
大変ありがとうございました。最後に、今後のキャリアについて、復帰後にチャレンジしたいことなどがあれば教えてください。
(萩原)
先輩社員の方々のように、たくさんの案件の経験を積んで、何か問題が起こった時も、たくさんの引き出しから自分で解決策を柔軟に見つけ、これまで以上に先方政府側ともスムーズにコミュニケーションをしていけるようになりたいです。また、CAJはこれまでの仕事内容以外の分野にも拡大していこうとしているので、私もどんな新しい仕事でも、常に挑戦し、学び続けていきたいと思っています。新しいことに挑戦できることが大変楽しみです。
■おわりに:社員一人ひとりの人生に寄り添って
今回のインタビューを通じて、CAJの業務に真摯に取り組む社員のリアルな姿、そして柔軟で温かみのある職場文化の一端を感じていただけたのではないでしょうか。キャリアの継続とライフイベントの両立は、どちらも人生において大切なテーマです。私たちクラウンエイジェンツ・ジャパンは、「えるぼし三つ星」の認定にふさわしい、誰もが安心して働ける環境をこれからも追求してまいります。